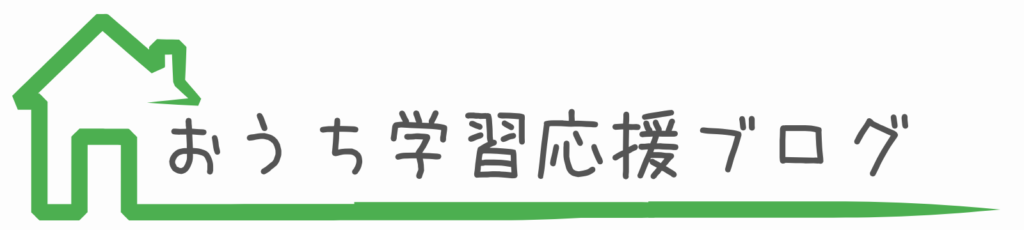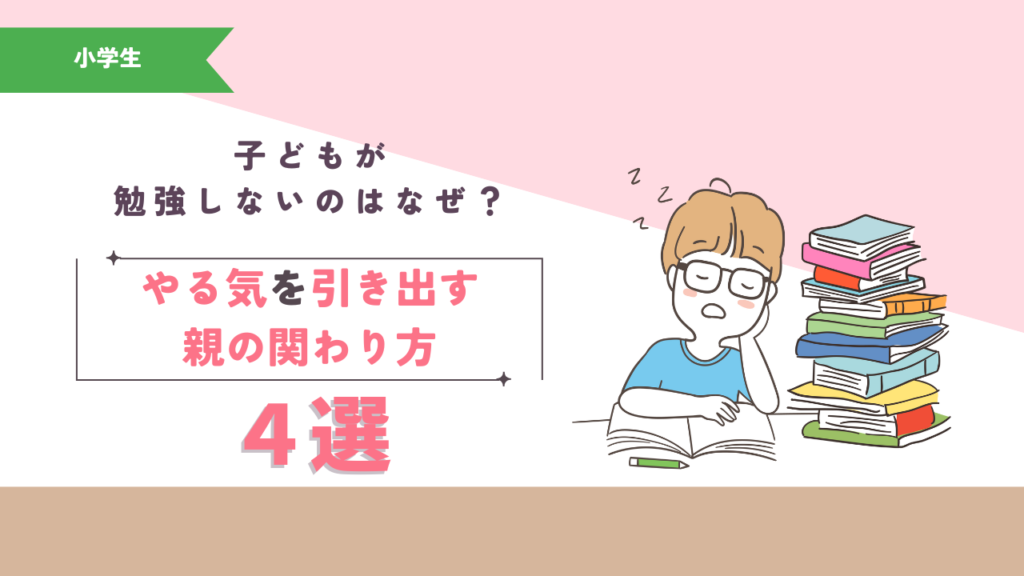「宿題やった?」と聞けば、「あとでやる〜」
でも結局やらなくて、こっちはイライラ…。
ゲームや動画には夢中なのに、勉強は5分と続かない。
「勉強しなさい!」って言いたくないのに、気づけば毎日言ってしまう。
そんなふうに悩んでいませんか?
実は、「勉強しない子」にはそれぞれに理由やタイプがあるんです。
その原因を知り、逆効果になりがちな親の対応に気づくだけで、子どものやる気は少しずつ変わっていきます。
私自身、3人の子どもを育てながら、元教員として多くの親御さんと関わってきましたが、「勉強しなさい」をやめたことで、子どもが自分から勉強に向かうようになった例もたくさんあります。
この記事では、
- 勉強しない子に多いタイプの特徴
- 親がやりがちなNG対応とその理由
- 自分から勉強するようになる家庭での工夫
をわかりやすく紹介します。
「うちの子も、いつか自分から机に向かってくれるようになるかな…」
そんな気持ちがある方は、きっとヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
勉強しない子のタイプとは?やる気が出ない理由をチェック
子どもが勉強しない理由は、実は1つではありません。
「面倒だから」だけでなく、性格や環境、感じているストレスなど、さまざまな要因が関係しているんです。
まずは、お子さんがどのタイプに近いのか、当てはまるものがあるかをチェックしてみましょう!
① 勉強の意味を理解していないタイプ
- 「なんで勉強しなきゃいけないの?」とよく聞いてくる
- テストの点が悪くても気にしない
「勉強=未来につながる」と実感できていないと、やる気は出にくいものです。
② 集中力が続かないタイプ
- 机に向かってもすぐに立ち歩く
- 気が散って他のことを始めてしまう
集中力の問題は環境や学習時間の長さも影響します。
③ 苦手意識が強く、やる気が出ないタイプ
- 「わからない」とすぐにあきらめてしまう
- テストで低い点数を取ることが多い
「できない」が続くと、やる前からあきらめてしまいがちに。
④ 疲れやストレスが原因のタイプ
- 「疲れた」「もう無理」と言ってすぐに休みたがる
- イライラして反抗的な態度をとることも
学校や家庭の疲れがたまっていると、勉強に向かう余力がなくなってしまいます。

うちの子、どれも当てはまる気がする…



実はそれが普通なんです!タイプは複数当てはまることもあるし、日によって変わることも。
勉強しない子に逆効果な親の対応とは?NG行動4選
子どもが勉強しない理由が分かったら、次に気をつけたいのが「親の関わり方」。
実は、良かれと思ってやっていることが、子どものやる気を奪ってしまうこともあるんです。
ここでは、やりがちなNG行動を4つ紹介します。
心当たりがある方は、今日から少しずつ変えていけば大丈夫です!
NG行動① 「勉強しなさい」
「宿題やりなさい。」って言ったのに、動かない。
ようやくやり始めたと思ったら、ブツブツ文句を言いながら雑にやる…。



結局、言わなきゃやらないし。言わなかったらもっとやらなくなる気がして言っちゃうよね。



分かります!でも「やらされ感」が強いと、勉強がイヤなものに。伝え方を少し工夫するだけでも反応が変わってきますよ。
命令口調は、子どもにとってプレッシャー。
「自分でやると決めた」気持ちを大事にしたほうが、やる気につながります。
NG行動② 教材を親が選ぶ
「このドリル、あなたにピッタリだから!」と渡しても、子どもは渋い顔。



せっかく子どもに合いそうなの選んだのに、なんでやりたがらないの?



子どもって、自分で決めたことのほうがやる気が出るんです。「どっちのドリルにする?」って選ばせるだけでも変わりますよ。
自分で選んだ教材や課題のほうが、「やらされてる感」が少なくなり、やる気につながります。
まずは、選ぶところから関わらせてみましょう!
NG行動③ ガミガミ言ってしまう
「もう!またやってないじゃない!」
「やらなきゃ困るのはあなたでしょ!」
気づけば毎日こんな言葉をかけていませんか?



叱りたくないのに、ついイライラして言っちゃうんだよね…



私も何度もガミガミ言ってしまって、あとから自己嫌悪になることがあります。そんな時はまず、「どうしてやらなかったのか?」を聞いてみるのが効果的ですよ。
叱られることで、「勉強=怒られるもの」というイメージがついてしまうと、どんどんやる気がなくなってしまいます。
NG行動④ 結果だけをほめる
「100点取ってすごいね!」
これ、言っていませんか?



言ってる!だって、100点はすごいことだよ!



確かに、すごいことです。もちろん褒めるのは大切ですが、「結果だけ」を褒め続けると逆効果になることもあるんです。
例えば、「100点だなんてすごい!」と言われると、子どもは 「高得点じゃないとダメ」 と思い込んでしまいます。
その結果、プレッシャーから カンニングをしてでも高得点を取ろうとする ことも…。
といったように、努力や工夫をしっかり見てあげることが、やる気の土台になります。
勉強しない子が変わる!家庭でできるやる気アップ法
「勉強しなさい!」って言わなくても、子どもが自分から机に向かってくれたら嬉しいですよね。
ここでは、私が実際に家庭や教員時代に試して効果があった工夫を4つご紹介します。
1. 勉強を「楽しいもの」に変える
子どもって、「面白そう!」と思ったことにはぐんぐん夢中になりますよね。
それなら、勉強だって“遊び感覚”で取り入れてしまいましょう!



うちの子でも勉強楽しめるのかな?そんな方法あったら知りたい!



私の子どもたちも、遊びっぽくしたら見違えるように取り組みました。おすすめは「学校ごっこ」です。
「学校ごっこ」で勉強タイムを楽しく
我が家では「おうち学校」と名付けて、ちょっとした学校ごっこを取り入れています。
- 授業時間や教科を子ども自身に決めさせる
- 宿題をリュックに入れて登校
- スマホでチャイム音を流すと本格的な雰囲気に!
小学校低学年なら、「〇時から1時間目」など、時間の感覚も自然と身につくメリットがあります。
興味のあることと勉強をつなげる
- 料理好き → レシピで分量の計算
- サッカー好き → 選手データで算数問題づくり
- 恐竜好き → 図鑑からカタカナや知識を吸収
子どもの「好き」から広げると、「やらされる勉強」が「やってみたい学び」に変わります。
タブレット学習
進研ゼミのチャレンジタッチやスマイルゼミなど、ゲーム感覚で取り組める教材を使うのもおすすめです。
教員時代、タブレットを活用することで集中力が続くようになった子がたくさんいました。みんなタブレット大好きなんですね。
わが家でもタブレット学習は大活躍でした。わが家で使ったのは進研ゼミのチャレンジタッチ。
気になる方はこちらをチェック!【進研ゼミ小学講座】チャレンジタッチ体験動画
2. 選択式で、自分から取り組めたという体験を積ませる
やる気を引き出すカギは、“自分で決めた”という感覚。
ちょっとした選択肢を与えるだけで、子どもはぐっと前向きになることがあります。



自分で決めるって言っても…結局ダラダラしちゃうんじゃないの?



意外と「選ばせる」って効果ありますよ。「どっちがいい?」って聞くだけでも、取りかかりやすくなるんです。
まずは、勉強方法を選ばせてみましょう。
- 「算数と国語、どっちからやる?」
- 「リビングでやる?自分の部屋にする?」
「どっちもイヤ」と言われたら、別の選択肢を提示してみましょう。たくさんの提案をしたとしても、選ぶことができたらOKです!
選んで取り組めたら、声をかけて「成功体験」にかえてあげます。
- 「この計算、昨日より速くなったね!」
- 「昨日より漢字がきれいに書けてるよ!」
小さな成長も見逃さず、認める声かけをしてあげましょう。
苦手な分野ほど、しっかり認めてあげると、自信につながりますよ。
3. 勉強開始のハードルを下げる
「勉強=めんどくさい」と感じている子には、スタートのハードルを下げる工夫が効果的です。



最初の一歩が重いんだよね。



その「やるまでの一歩」を軽くしてあげるのがコツ!始めたら意外とスムーズに進むことも多いんですよ。
短時間から始める
- 「5分だけやってみよう!」
- 「1問だけ解いてみよう!」
「やってみたら案外できた」という感覚がやる気につながります。
目に見える目標をつくる
- 「このページが終わったらおしまい」
- 「5日続いたらシールを貼る」
達成感を感じやすくなる“見える目標”は、モチベーション維持に効果的です!
4.やらざるを得ない環境をつくる
毎日「勉強しなさい!」と声をかけ続けるのは疲れますよね。
でも、環境をちょっと工夫するだけで、子どもが自然と勉強するようになることもあるんです。



声かけなしで勉強してくれるようになったら、ラクなんだけど…



学習スペースや道具の置き方をちょっと変えるだけでも、行動がスムーズになるんです。私も実践してますよ!
「見える化」で自然に始めやすくする
- 机の上にドリルと鉛筆をセットしておく
- やるページを開いておく
「今からやるもの」が視界にあると、取りかかりやすくなります!
家族が勉強する姿を見せる
親が読書や勉強をしていると、子どもも「自分もやろうかな」と自然にマネすることも。
同じ空間で勉強する時間をつくるのもおすすめです。
まとめ|やる気スイッチは関わり方で変わる!
子どもが勉強しないと、つい不安になったり、イライラしてしまうこともありますよね。
でも、「勉強しない」には必ず理由があって、親の関わり方ひとつで、やる気が少しずつ変わってくるんです。
この記事では、
- 勉強しない子の“4つのタイプ”と原因
- 逆効果になりがちなNG対応
- 家庭でできるやる気アップの具体的な工夫
を、元教員・3児ママの視点からお伝えしました。
「今日からこれをやろう」と思えることが、ひとつでも見つかっていたら嬉しいです。
わが家の小学生は、進研ゼミを使ってやる気スイッチを入れました。
こちらから公式サイトをチェックしてみてくださいね。