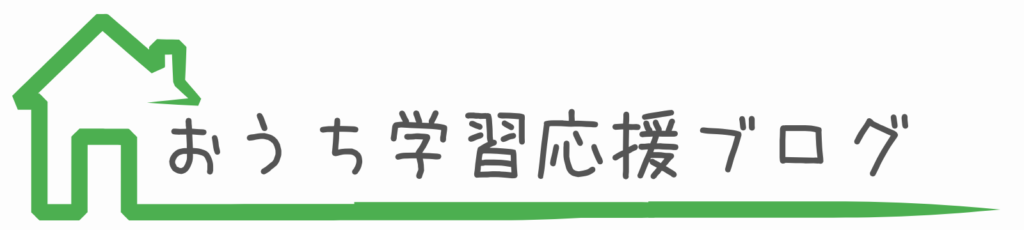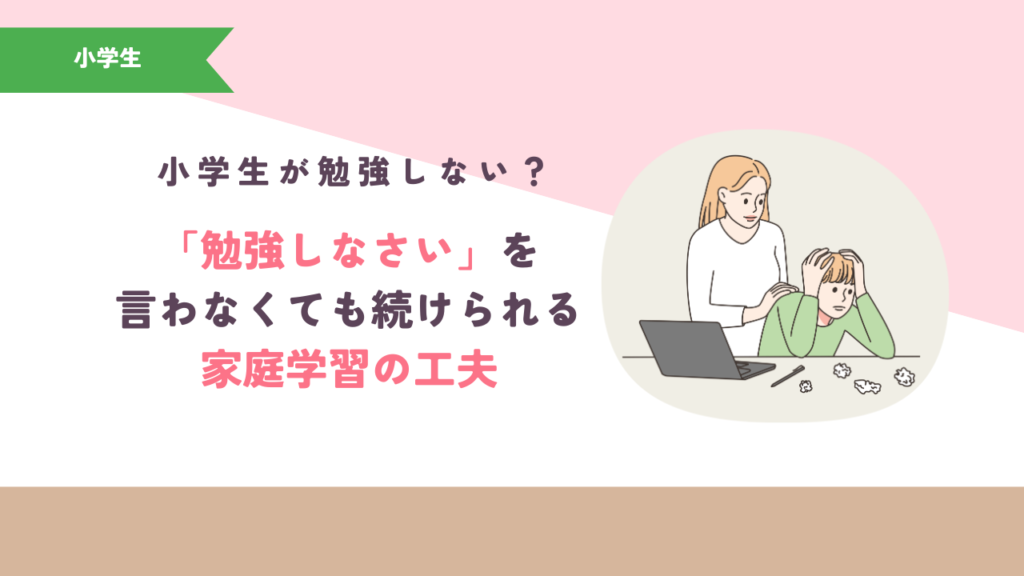「勉強しなさい」と言わなくても、子どもが自分から勉強してくれたら──
そう思ったこと、ありませんか?
小学生の家庭学習でよくあるのが、
- 「言わないとやらない」
- 「声をかけても続かない」
という悩み。
私自身も、子どもに毎日のように「勉強しなさい」と言いながら、イライラと自己嫌悪をくり返していました。
「やらせる勉強」があたりまえになってしまう毎日に、モヤモヤしていたんです。
でもあるとき、学習スタイルを少し変えたことで、子どもの勉強への意識に少しずつ変化が──
「今日はこれをやるよ」と、自分から取りかかる日が増えていったんです。
この記事では、小学生の子どもが『勉強しない』状態から、『勉強するのがあたりまえ』になるまでの家庭での工夫を、元教員×3児ママの体験をもとにご紹介します。
「勉強しなさい」を言わずにすむ毎日に変えるヒントが、きっと見つかるはず。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
小学生が勉強しない理由|やる気じゃなく『仕組み』が原因
「うちの子、小学生になったのに、なんでこんなに勉強しないんだろう…」
「昨日はやったのに、今日はもう忘れてる」
「“勉強しなさい”って言わないようにしたいけど、言わなきゃ動かない」
家庭学習の悩みって、わかっているのに動けない子どもへのモヤモヤがほとんどじゃないでしょうか。
でもそれって、本当に子どものやる気や性格のせいなんでしょうか?
実は、小学生の「勉強しない」には共通点があります。それは、「何を、どれだけやればいいか」が見えていないこと。
大人でも、「とりあえず走ってみて」と言われたら、スタートしづらいですよね。ゴールやペースが見えないと、始める気持ちが湧いてこないんです。
だから、
小学生の勉強が続かないのは、意志が弱いからじゃない。続けられる仕組みがないだけなんです。
この視点に気づいてから、わが家の取り組み方も少しずつ変わっていきました。
「勉強しなさい」が口ぐせだった頃の失敗と気づき
「今日は宿題、もうやったの?」
「さっきやるって言ったよね?」
「ゲームの前に、まずは1ページ終わらせようよ」
——そんな声かけを、何度くり返したかわかりません。毎日のように「勉強しなさい」を口にしていました。
なるべく穏やかに言おうと心がけてはいるけれど、思うように動かない子どもを前にすると、ついイライラしてしまう。
そしてそのあとにやってくる自己嫌悪…
「勉強させること」に親のエネルギーが注がれてしまう。
そんな毎日でした。
子どももきっと、「やらされている」と感じていたと思います。
だから、どこか不機嫌そうだったり、ダラダラしてしまったり…。
がんばってほしいと思っているのに、うまく伝わらない。
「どうしたら、“勉強しなさい”を言わなくても、やる子になるんだろう」
ずっと、その答えを探していました。
「勉強しなさい」を言わなくても勉強する子に変わった理由
わが家では、通信教育の進研ゼミを使いながら、少しずつ「やらされる勉強」から「自分からやる勉強」に変わっていきました。
その理由は、大きく3つあります。
①「今日はこれだけやればいい」が明確だったから
やる内容と量が決まっているだけで、子どもは迷いません。
“とにかく何かやって”ではなく、「今日はこのページだけやればOK」と具体的に示されていることが、勉強のハードルをぐっと下げてくれたのです。
最初は親が「ここまでだよ」と一緒に確認していましたが、慣れてくると子ども自身が「今日はこのページ」と把握できるようになりました。
この「小さなゴールが見える」ことが、毎日の継続につながっていったんです。
②「やったら終わり」じゃなく、成長を見せてくれたから
進研ゼミでは、がんばりを見える化する仕組みがいくつも用意されています。
赤ペン先生の返信や努力賞ポイントなど、「ちゃんと見てるよ」「頑張ったね」と伝えてくれる仕掛けがある。
これが、ただ終わらせるだけだった勉強を、「やってよかった」と感じられる時間に変えてくれました。
親以外の誰かが見てくれている安心感が、モチベーションの安定にもつながったと感じます。
③「毎日やる」があたりまえの流れになったから
大事だったのは、「やる気があるからやる」ではなく、“やるのが日課”という状態をつくること。
進研ゼミの教材は、1回に取り組む量が多すぎず、サクッと終えられる工夫がされています。
子どもにとっても「これくらいならやってもいいか」と思えるボリュームだったからこそ、毎日の中に自然と組み込まれていきました。
やるのがあたりまえになったのは、進研ゼミの仕組みにあった
進研ゼミを使い始めて実感したのは、子どもが「自分からやる」ようになるための仕組みが、ちゃんと整っているということでした。
「習慣」は、やる気だけではなかなか続きません。やる気がなくても自然と手が伸びるような仕組みがあるかどうかがカギなんですよね。
これは大人の習慣づくりとまったく同じです。
わが家の子どもたちが「やらされる」状態から、「今日はこれをやろうかな」と自分で動き出せるようになったのは、まさにこの進研ゼミの“習慣化のしくみ”があったからだと感じています。
毎日のレッスンがの量がちょうどいい
1回の学習時間が短く、「これならやれそう」と思える分量になっています。
特に低学年であれば、1回10分程度で完了するよう設計されているので、始めるハードルが低く、達成感も得やすいんです。
そんな気持ちが自然と湧いてくるから、“続けたくなる”流れができていくんですね。
「今日はこれをやればいい」が明確
チャレンジタッチ(タブレット学習)なら、その日のおすすめレッスンが画面に表示されます。
これって、学習習慣がまだ定着していない子にとって、とても大きなポイントです。
タブレットを起動させればやるべき学習に導いてくれるから、勉強に取り組むハードルが下がり、自然と始められます。
これから小学生になるお子さんや、低学年のお子さんに特におすすめです。
チャレンジタッチの「おすすめレッスン」ってどんな感じ?
実際の画面や流れが気になる方は、こちらの体験ページを参考にしてみてくださいね。
続けたくなる仕掛けが、さりげなくある
- 学習後に褒めてもらえる演出
- シールやスクラッチのごほうび
- がんばりに応じてたまる「努力賞ポイント」
など、
「できた!」を感じられる演出があちこちにちりばめられています。
この「ちょっと楽しい」「認めてもらえる」という体験が、子ども自身の“やってみようかな”の気持ちに火をつけてくれるんです。
その子に合った学び方が選べるから、ムリなく続く
実はわが家では、最初はチャレンジタッチから始めて、途中から紙教材に切り替えました。
どちらにもメリットはあります。
- チャレンジタッチ:キャラクターの声かけや動画解説で、親の手をかけずに学べる
- 紙教材のチャレンジ:自分の手で書くことで、じっくり学べる
進研ゼミはネットから学習スタイルの変更が簡単にできるので、子どもの成長や好みに合わせてスタイル変更しながらムリなく続けやすいのも魅力です。
習慣って、「がんばって続けるもの」ではなく、やるのが自然な状態になること。
進研ゼミは、その自然な習慣を作るための仕組みが整っている教材でした。
小学生が勉強しない毎日から、“やるのがあたりまえ”へ
気づけば、「今日は勉強やったの?」と声をかけることが、ぐんと減っていました。
代わりに聞こえてきたのは、「今日はここまで終わったよ!」という、子ども自身の声。
それはまさに、
『やらされる勉強』から『自分でやるのがあたりまえ』に変わった瞬間
でした。
- 「小学生がなかなか勉強しない」
- 「毎日“勉強しなさい”と声かけするのがしんどい」
そんな日々を、私も経験してきました。
でも今思えば、習慣って「がんばること」じゃなく、毎日の中に“自然に組み込まれる仕組み”をつくることだったんですよね。
その仕組みを整えてくれたのが、進研ゼミでした。
進研ゼミは、親の声かけの負担を減らしながら、子どもが「これならできそう」と感じられるきっかけを用意してくれる教材です。
もし今、
- 毎日の声かけに疲れている
- 勉強しない子どもにどう向き合えばいいのか悩んでいる
そう感じているなら——
一度、試してみるのもひとつの手かもしれません。
\ やらされる勉強を“やるのがあたりまえ”に! /