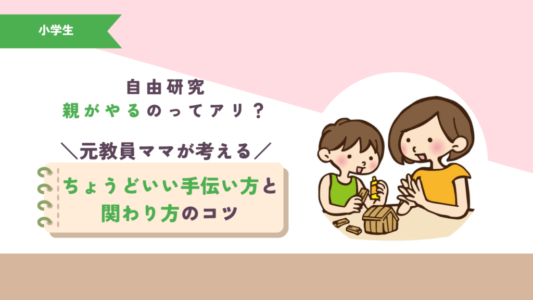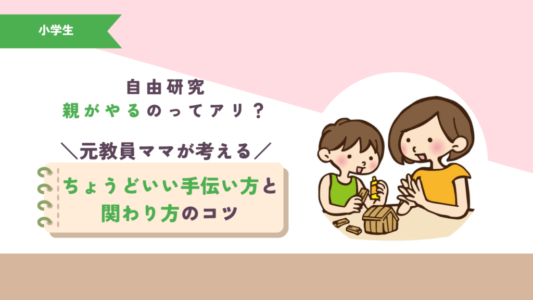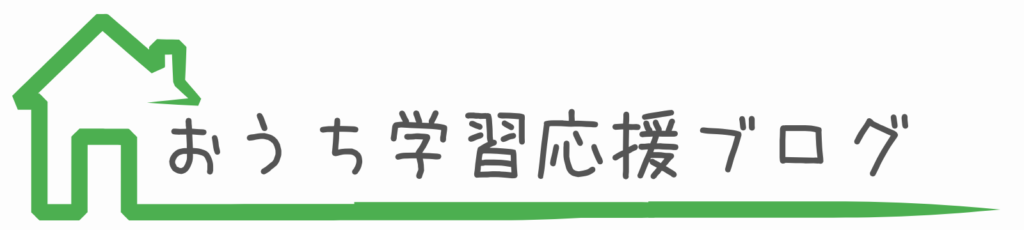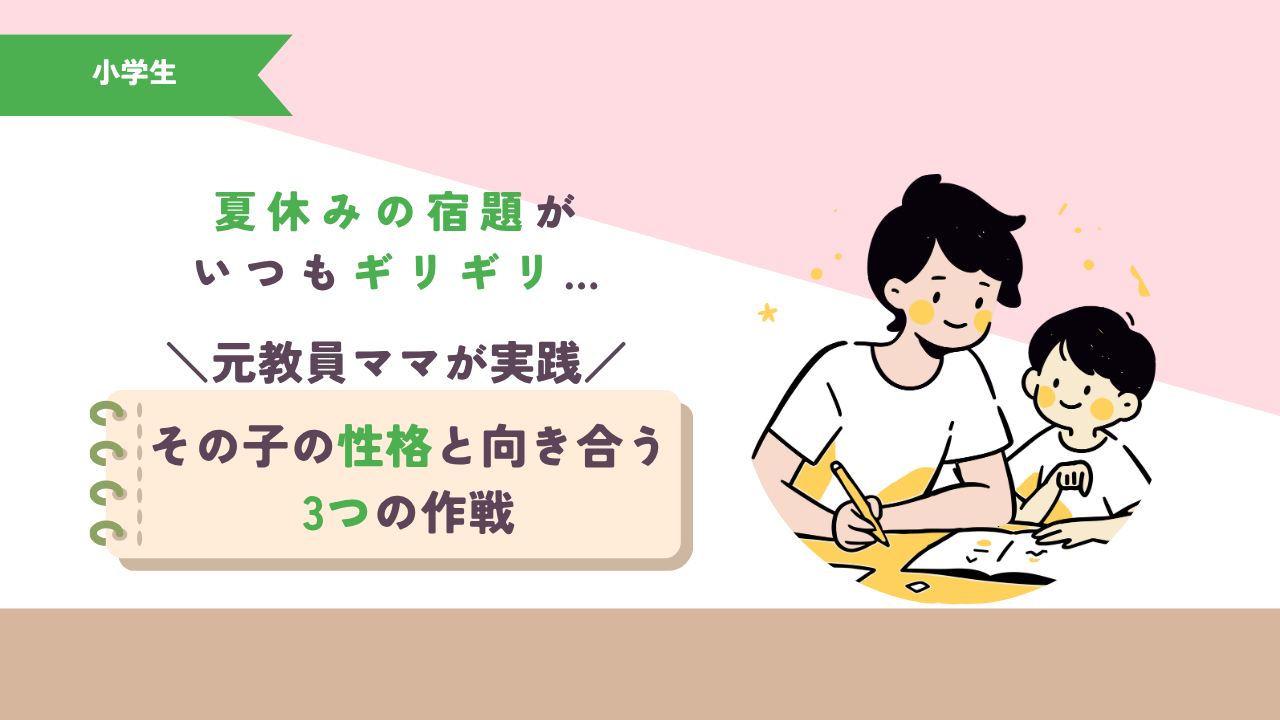夏休みの宿題、いつもギリギリ…
今年こそ計画的に終わらせたいのに、うまくいかない
そんな悩み、実は“性格のせい”だけではないんです。
小学生はまだ、自分で立てた計画を“続ける力”が育っている途中。うまくいかなくても、それは当たり前のことなんです。
とはいえ、「また今年も…」「どう声かけたらいいの?」と悩むのも本音ですよね。
この記事では、元教員ママ×3児子育て中の私が、「夏休みの宿題がギリギリになってしまう子」のパパやママに向けて、計画的に終わらせるための3つの工夫と関わり方をやさしく解説します。
 きみどり
きみどり今年の夏こそ、親子で「計画的にできた!」を目指してみませんか?
【誤解してない?】夏休みの宿題が終わらない理由は“性格”じゃない
「なんで計画通りに進められないの?」
「やるって言ったのに…」
そんなふうに思ってしまうこと、ありませんか?
小学生にとって、「計画を立てる」ことと「その通りに進める」ことは、まったく別の力。
最初はやる気まんまんでも、途中で計画倒れになってしまうのは、実はよくあることなんです。



計画を立ててもうまくいかないのは、年齢的な特性としてごく自然なことなんです。
たとえば、小学生の多くは、
- 宿題の量をざっくりとしか把握できない
- 「今日やらないと後で大変」という見通しを持てない
- やる気の波に左右されやすい
こうしたことがまだ苦手です。
つまり、宿題が計画通りに進まないのは、性格や努力不足のせいではなく、脳の発達段階によるものなんです。
だから、うまくいかないからといって、「ちゃんとやらせなきゃ」と焦る必要はありません。
夏休みの宿題を“ギリギリにしない”3つの親子サポート術
小学生が夏休みの宿題を計画的に進めるには、親のサポートが必要です。
とはいえ、親が全てを管理してしまったら、子どもの「計画を立てて実行する力」が育ちません。
そこでカギになるのが、「しくみ」や「環境づくり」。
ここでは、わが家でも実践して効果があった、3つの工夫をご紹介します。
コツ①:宿題の全体量と難しさを一緒に確認して、計画を立てる


「夏休みの宿題が終わらない…」を防ぐには、まずは親子で全体量を一緒に確認することから始めましょう。
「どんな宿題が、どれくらいの量あるのか」が見えることで、子どももゴールを意識しやすくなります。
さらに大切なのが、「この宿題、自分ならどれくらい時間がかかりそう?」を一緒に考えること。
たとえば、漢字テストのプリントが3枚、計算プリントが6枚あるとします。
このとき、ただ「全部で9枚あるから、1週間で終わるかな」と量だけで見積もるのではなく、プリント1枚終わらせるのに子どもがどれくらいかかるか、具体的に一緒に考えていきましょう。
- 「漢字は1枚30分かかりそう」
- 「算数はけっこう時間がかかるから、1枚で30分以上かも」
というタイプのお子さんなら、1日1枚ずつコツコツ進める方が現実的。
逆に、
- 「漢字は10分くらいで終わる」
- 「計算もわりとすぐ終わるよ」
というお子さんなら、1日2枚ずつ進めていく方法もアリですよね。
こうして、量だけでなく“かかる時間”も見積もりながら、ペースを一緒に考えることで、子どもにとって無理のないスケジュールが見えてきます。



また、計画を立てるときは、「どれからやりたい?」と子どもに選ばせるのもおすすめ。自分で選ぶことで、取り組む意欲がぐっと高まります。
作った計画は一覧にして見えるようにしておくのがおすすめです。
終わったら○をつけたり、シールを貼ったりするなど、進み具合が“目に見える形”になると、「できた!」の実感にもつながりますよ。
コツ②:生活の一部に“宿題タイム”を組み込む
せっかく立てた計画表。できるだけ実践できるようにしていきたいですよね。
とはいえ、「○月○日は漢字プリント1枚とドリル2ページ」など、日付単位で組むだけだと、小学生にとってはハードルが高いものです。
そこでおすすめなのが、生活リズムと結びつける方法。
たとえば、
- 朝ごはんのあとにドリル
- お風呂の前にプリント1枚
というように、「何時にやるか」ではなく、「いつもの行動のあとにやる」と決めることで、“やるのがあたりまえ”の流れができて、習慣化しやすくなります。
さらに、一日の終わりにはふり返りタイムを設けるのもおすすめ。
「今日の予定、どうだった?」「ここは無理があったかな?」と親子で話してみるだけでも、自分で計画を見直す意識が育ちます。



たとえば、「お風呂の前は忙しいから、夜ごはんのあとにやる方がよさそう」など、子ども自身が気づけるようになると、計画を“自分ごと”として実行しやすくなりますよ。
コツ③:うまくいかない日もOK!リカバリーを一緒に考える
どんなに丁寧に計画を立てても、毎日その通りに進むとは限りませんね。
やる気が出ない日もあるし、予定がずれることもあります。
でもそれは、ごく自然なこと。
うまくいかない日があるからこそ、「どう立て直すか」を一緒に考えるチャンスになるんです。
そこで大切なのが声かけの仕方。
| NG | OK |
|---|---|
| 今日のできなかった分、ちゃんと明日やりなさいよ | 今日、できなかったね。じゃあ明日はどうする? |
| NG | OK |
|---|---|
| ペース上げないと終わらないんじゃないの? | ちょっと終わらせるのきびしそうだね。何が難しい? |
このように、できなかったことを否定するのではなく、次に向かうヒントや改善点を見つけるきっかけになるような関わり方が大切です。
そして、少しでも前に進んだら、小さくてもその努力を認めてあげることがとても大切。
「今日1ページ進んで、よかったね」「計画見直せたね」
そんな積み重ねが、子どもの自信になっていきます。
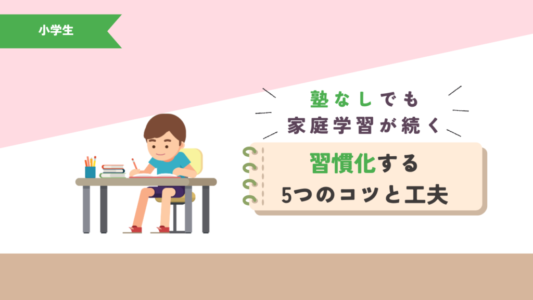
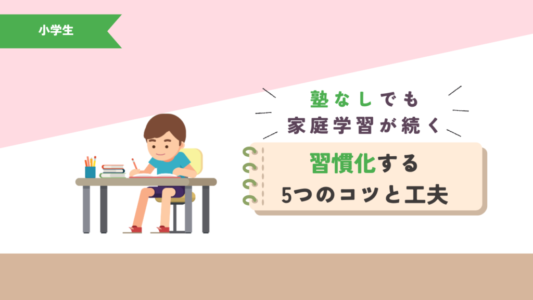
「ちゃんとやってる?」と言いたくなったときにできる見守り方
計画を立てたあと、親はどこまで手を出すか――これ、悩みますよね。
「やったの?」「進んでるの?」と聞きすぎても不機嫌になるし、放っておくとまったく進まない…。
ここでは、わが家でも試行錯誤して見えてきた、ちょうどいい見守り方をご紹介します。
声かけは結果より過程に目を向ける
「宿題、終わった?」よりも、「今日はどこまでできた?」と聞いてみると、子どもは安心して、ちゃんと話してくれます。
失敗してもいい。
- 「どこで止まっちゃったの?」
- 「どうしたら続けられそう?」
そんな声かけがあると、自分で考える力も少しずつ育っていきます。
うまくいかない日は、励ましより共感を
「がんばれ!」と言いたくなる気持ち、すごくよく分かります。
でもうまくいかない日こそ、まずは「そっか、今日はしんどかったね」と寄り添ってあげるだけで、子どもはほっとします。
そして「明日はどうする?」と次を考えるタイミングを、一緒に見つけていければ十分です。
「見てるよ」の一言が、いちばんの応援になる
子どもって、思った以上に「親に見ててほしい」んですよね。
- 「今日、集中してたね」
- 「そのやり方、考えたんだね」
- 「昨日よりテンポよくできてたよ」
こんな一言があるだけで、「ちゃんと見てくれてる」が伝わって、またがんばろうって思えるものです。



うまく進めること以上に、「自分でやってみよう」と思えることを応援していく。そんな親の姿勢が、宿題のやりとりを通して、子どもの自信を育ててくれます。
「宿題が終わらない…」を卒業するために、親ができること
「今年こそ、計画的に宿題を終わらせたい」
そう思っても、なかなかうまくいかないのが小学生の夏休み。
でも実は、やる気や性格ではなく、“しくみ”と“関わり方”を少し工夫するだけで、大きく変わってきます。
- 宿題の量や難しさを一緒に確認して
- 毎日の生活に自然と組み込んで
- うまくいかない日も、親子でふり返る
この3つを意識するだけで、「やらされる宿題」から「自分で進められる宿題」へと変わっていきます。
完璧じゃなくても大丈夫。今年の夏は、子どもが「できた!」を積み重ねていける夏にしていきましょう。