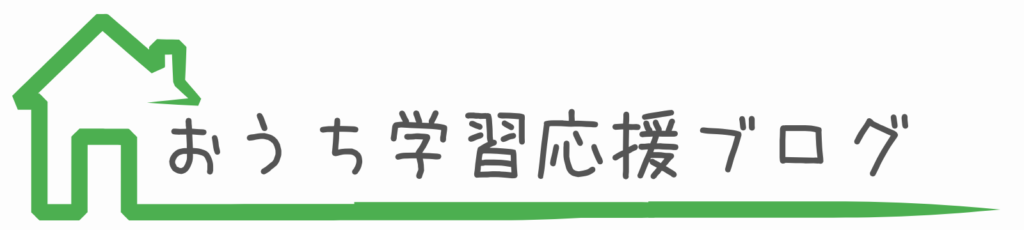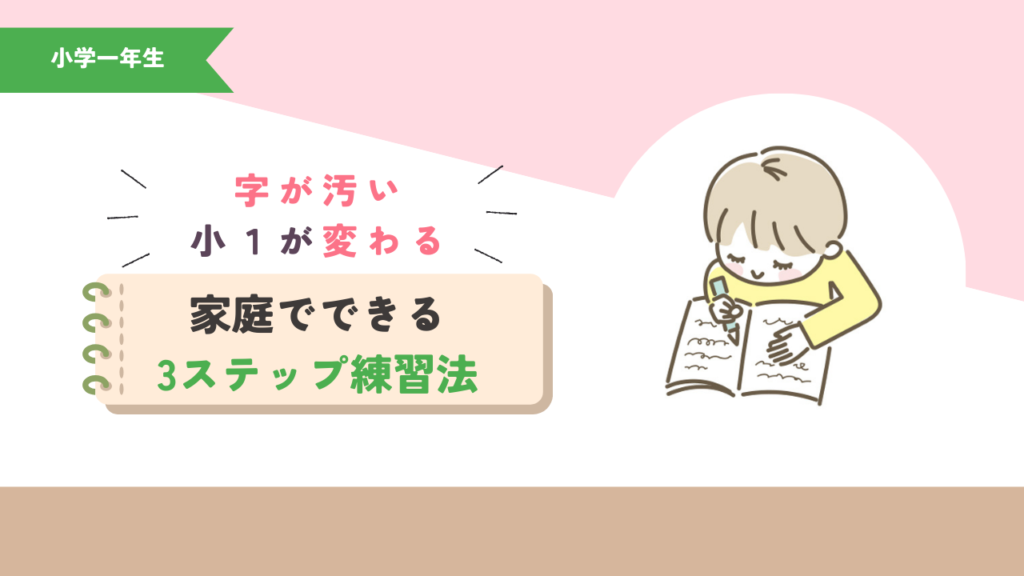うちの子、字が汚い…
小学1年生のノートや宿題を見て、そう感じることありませんか?
- マスからはみ出している。
- 形が崩れて読みにくい。

つい「もっと丁寧に書いて」って言いたくなっちゃうよね



分かります。でも安心してください。小1で字が汚いのは、よくあることなんです。ちょっとした工夫で、きれいな字を目指せますよ。
この記事では、家庭でできる、簡単な練習方法3ステップを紹介します。
- 「毎日どんな練習をしたらいい?」
- 「親はどこまで口を出して大丈夫?」
そんな疑問にも答えていきます。
字が汚い原因は?小1によくある3つの理由
小学1年生は、まだ字を書く基礎が育っている途中。
崩れた字や読みにくい字になってしまうのが当たり前なんです。
小学1年生の字が汚くなってしまう主な理由を、詳しく見ていきましょう。
- 姿勢や鉛筆の持ち方が安定していない
- 字の大きさやマスの使い方が分からない
- 勉強よりも、遊びたい気持ちが優先されがち
姿勢や鉛筆の持ち方が安定していない
小学1年生の子どもは、まだ体幹の筋肉が十分に発達していません。背筋を伸ばして座り続けるのは難しく、すぐに前かがみになったり、肘をついたりしてしまいます。
姿勢が安定しないから、手先に余計な力が入り、線が曲がったり字が乱れたりするのです。



まずは、「正しい姿勢を維持するのが難しい年齢なんだ」と理解してあげましょう。
さらに、手や指の筋力も未発達。鉛筆をしっかり安定させるのも難しいんです。
三本の指(親指・人さし指・中指)で支える「三点持ち」が理想ですが、力が足りず鉛筆がグラグラしたり、逆にギュッと握り込んで疲れてしまったりすることもあります。
こうした手先の未熟さが、字の形の不安定さにつながっているのです。
字の大きさやマスの使い方が分からない
小学1年生は、まだ「どのくらいの大きさで字を書けばちょうどよいのか」をつかめていません。だから、マスからはみ出してしまったり、逆に小さすぎて読みにくくなったりしがち。
国語や算数のノートは、最初は大きなマスを使いますが、マスの中に字をおさめるのは、子どもにとっては意外と難しいもの。なぜなら、
- マスの真ん中に字を書く
- 上下左右の余白をそろえる
といった感覚は、経験を積みながら少しずつ身につくものだからです。
また、字を構成するパーツのバランスをイメージする力(空間認知)も、まだ発達の途中。
「横棒が長すぎる」「丸が小さすぎる」といったアンバランスさが出やすいのは、そのためです。



小学1年生は「字の形を頭でイメージして、それを手で表現する力」を、育てている最中。字のバランスがとれないのは自然のことなんです。
勉強よりも、遊びたい気持ちが優先されがち
小学1年生の子どもにとって、遊びは生活の中心。「きれいに字を書く」よりも「早く宿題を終わらせて遊びたい」という気持ちが先に立つのは、ごく自然な姿です。
その結果、ノートを丁寧に書くよりも、とにかく終わらせることを優先してしまい、字が雑になってしまいます。
特に、ゲームやテレビ、外遊びなど「このあと楽しみが待っている」状況では、その傾向が強くなりがち。
また、思考スピードが、手の動きよりも早いため、「早く書いて次に進みたい」という気持ちから、どうしても筆圧や線のコントロールが甘くなってしまうことが多いんです。
つまり、「字が汚い」の裏には「遊びたい」「早く終わらせたい」という子どもらしい心理が隠れているのです。



字が汚いのは「能力が足りないから」ではなく、「成長の途中だから」。時間をかけて少しずつ練習していけば、必ず変わっていきます。焦らず、無理せず、サポートしてあげましょう。
家庭でできる!字がきれいになる3ステップ練習法



成長の過程だから字が汚いのはわかったけど、これからきれいな字が書けるように家で練習させたいな。
ここでは、家庭でできる簡単な練習方法を紹介します。
宿題とは別に、家庭で字の練習を取り入れてみたいときの参考にしてくださいね。
ステップ1:姿勢を整えよう
字が汚くなる大きな原因のひとつ、姿勢。
字を書く前に、まずはここをサポートしてあげましょう。
チェックするポイントは3つ。
- 足の裏が床についているか
- 背中が丸まっていないか
- ノートが体の正面に置かれているか
字を書く前は必ず、親子で「姿勢チェック」をする習慣をつけると効果的です。
声かけはシンプルでOK。
こんな合言葉にすれば、子どもも理解しやすくなりますよ。
リビングの椅子では足が床につかないことも多いので、足台や高さを調整できる椅子があると安心。
勉強のときだけでなく、食事のときにも姿勢を意識できるようになりますよ。
ステップ2:マスの中に書く練習をしよう
次はさっそく、書く練習です。
でも、子どもに任せてただ書かせるだけでは、なかなかできるようにはなりません。
そこで効果的なのが、
親がうすい線でお手本を書いて、子どもがなぞる練習です。
「どのくらいの大きさで書けばいいのか」を感覚的に身につきます。
慣れてきたら、全部を書かずに
- 一画目だけ書いて残りは子どもに任せる
- 書き始めの位置に点を打ってあげる
など、ヒントを少しずつ減らしていくのがコツ。
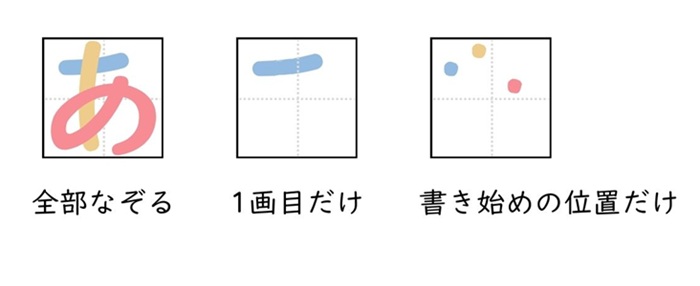
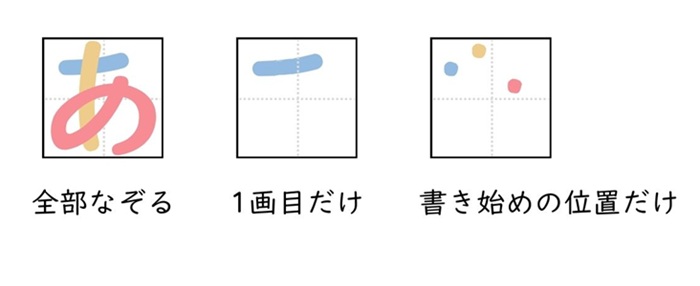
※画像のなぞる線は分かりやすくカラーにしていますが、実際は鉛筆でうすく書いてあげるだけでもOKです。
こうやって練習すると、だんだん自分でバランスをとって書けるようになっていきます。
この練習は1日3文字でもOK!1文字だけでも「うまく書けた!」という達成感を積み重ねていくことが大切。



辛くなってしまっては効果がないので、子どもの機嫌がいいときを狙って、無理なく取り入れてみてくださいね。
ちなみに、ノートを用意するなら、8マス~10マスがおすすめです
ステップ3:「できた!」を見える形で残そう
練習したら、必ず成果を見える形で残しましょう。
たとえば、
- きれいに書けた字に花丸をつける
- お気に入りのシールを貼ってあげる
こうして、「できた証」を残してあげれば、子どもの中に「できて嬉しい」という気持ちとともに達成感が生まれます。
この気持ちが、「また書きたい」という前向きな気持ちを育ててくれるんです。



前に書いた字と今日の字を並べて見せるのもGood!「成長してる!」と子ども自身が実感できます。この積み重ねが「きれいに書きたい」という気持ちを育ててくれますよ。
先生がよく使ってる採点ペン。シュッて丸をつけた時の音がよくて、テンション上がります。
練習だけじゃない!「字が汚い」を克服する方法



うちの子、座って練習するのは、すぐ飽きちゃう。練習させたいのに…
「字の練習をしよう!」と言うと、子どもはどうしても構えてしまいがち。
そこで、日常の中でできるの一工夫をご紹介!



遊び感覚で取り入れられるので、子どもも楽しんで続けられますよ。
ぬり絵、迷路、写し絵で運筆練習
迷路やぬり絵、写し絵は運筆の練習にぴったり。
せまい道を鉛筆でたどっていったり、線に沿ってなぞったりするうちに、「鉛筆を思い通りに動かす力」が自然についていきます。すると、字も自然と安定してきますよ。
誰かのために字を書く場面をつくる
誰かに読んでもらうという意識は、字を丁寧に書こうとする意欲につながります。
たとえば、
- お母さんのために買い物リストを書く
- お父さんに感謝の手紙を書く
など、生活の中で「誰かのために字を書く場面」を作りましょう。
書いてもらったら、「ありがとう!助かるよ」「とっても嬉しいよ」と感想を伝えるのを忘れずに。



書いたことを感謝される経験は、自信となり、「もっと丁寧に書いて伝えたい」という意識につながっていきます。
まとめ|小1の字は工夫次第でぐんと変わる
小学1年生で字が汚いのは、よくあることです。
まだ手や指の力が発達途中で、姿勢や持ち方も安定していないのが当たり前。「きれいに書く」より「早く終わらせたい」気持ちが強い子も少なくありません。
焦らず、無理のない範囲で、子どもの字の練習を取り入れられるといいですね。
家庭で字の練習を取り入れるときは、
- 姿勢と持ち方を整える
- 字の大きさをそろえる練習をする
- できた字を褒める
短い時間でも続けていくと、子どもの字は確実に整っていきます。
そして、「読める」「きれいに書けた」という実感が増えると、子どもは勉強そのものにも自信を持てるようになりますよ。ぜひお子さんと一緒に試してみてくださいね。
チャレンジタッチのひらがな学習なら、
飽きさせない工夫、自信を持たせる工夫がたくさん
\こちらもチェックしてみてくださいね/