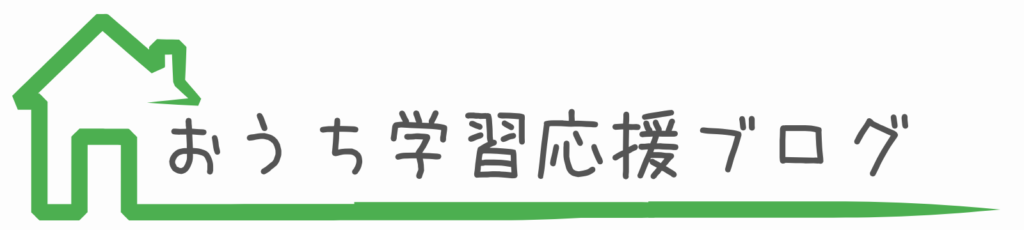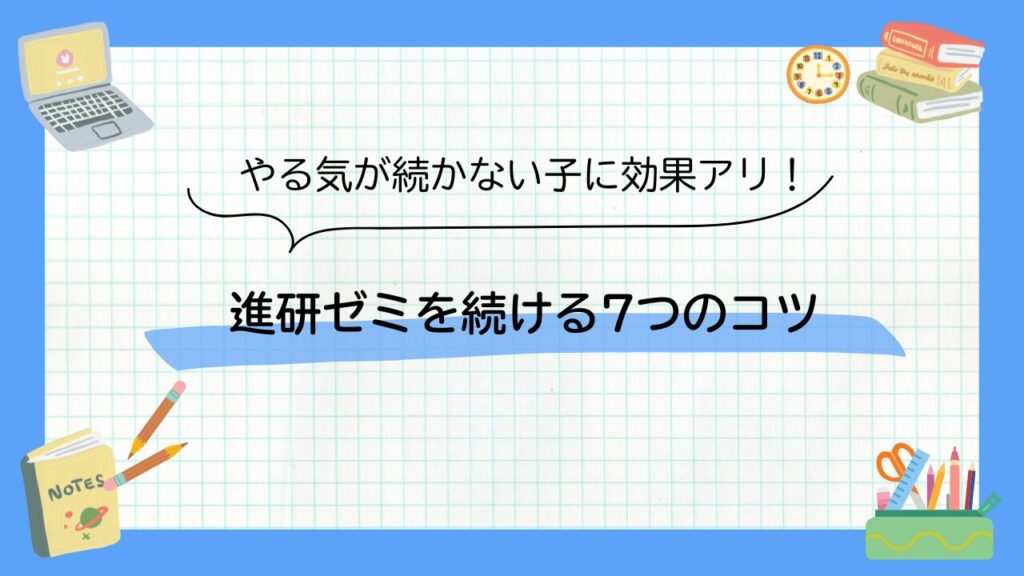「チャレンジタッチ、また後で〜」
そんな子どもの様子に、「早くやりなさい!」とつい言いたくなる。
でも、言えば言うほどやらなくなって、
気づけば教材がどんどんたまっていく…

最初はやる気満々だったのに、続かない。うちの子には向いてないのかな?続けても意味ないのかも…
わが家もまさに同じでした。長女が3〜4年生の頃はモチベーションにムラがあり、やる気が出ない日が続いていました。



でもある時、「進研ゼミを続けるコツ」は親の関わり方とちょっとした仕組みづくりだと気づいたんです。それから少しずつ、子どもが自分から進研ゼミに取り組むようになっていきました。
この記事では、
- 子どもが進研ゼミをやりたがらない理由
- 続かないときに見直したい親の関わり方
- わが家で効果のあった「進研ゼミを続けるコツ7選」
を、元教員で3児ママの実体験をもとに、わかりやすく紹介します。
「せっかく始めたのに続かない…」そんな悩みを感じている方のヒントになれば嬉しいです。



子どもが自分から動ける「やる気の土台」を一緒に作っていきましょう
無料体験&資料請求してみる!
進研ゼミが本当に合っているか不安な方は、まずは資料で教材の雰囲気を見てみるのがおすすめです。
冬限定キャンペーン中
\1月号受講費1,500円割引/
webでの体験はこちらから!
\今なら最大3,000円割引キャンペーン中/
進研ゼミが続かない理由|タイプ別にわかる「やらない」本当の理由
進研ゼミが続かないのは、やる気がないからではありません。
子どもには子どもなりの「やらない理由」があって、タイプによって対策も変わってきます。
ここでは、実際にわが家で見られたパターンや、よくある理由を紹介します。
面倒くさがりタイプ|「やらなきゃ」と思っても動けない
「やらなきゃ」と頭では分かっていても、なかなか行動に移せない——。
我が家の長女がまさにこのタイプでした。3〜4年生のころは、教材を前にしてもなかなか手が動かず、「あとでやる〜」が口ぐせに。
やる気がないわけではないのですが、「面倒くさい」「今じゃなくていい」が先に立ってしまうんですよね。
- 1問だけやってみよう
- シール1枚分だけやってみる?
など、とにかく始めてみるきっかけを作ってあげることで、流れに乗りやすくなります。
遊び優先タイプ|気づけば1日が終わっている
「やる気がないわけじゃないけれど、遊びが楽しすぎてつい忘れてしまう…」
我が家の長男がまさにこのタイプ。
チャレンジタッチに取り組むつもりではいても、遊びに夢中になって気づけば1日が終わっていた、ということが何度もありました。
例えばわが家では、
- 「このアプリ、一緒にやってみる?」と声をかけてみる
- 「今日やったらシール1枚だよ、どこに貼る?」と楽しみを提示する
- 「これ面白そう!ママがやっちゃおうかな〜」と笑いながら誘う
といったゆるくて楽しい声かけが意外と効果的でした。



「ちょっと一緒にやろうか?」という軽い提案が、行動のスイッチになることもあります。
難しく感じるタイプ|「わからない」からやりたくない
進研ゼミが続かない理由の1つに、「内容が難しいと感じて自信をなくしている」ことがあります。
「わからないから、やりたくない」
こう感じている子は、決してやる気がないわけではなく、“できない自分を見たくない”という気持ちが強いのです。



特に真面目な子や完璧主義な傾向のある子ほど、「間違えたらイヤ」「最初からできないと嫌」と感じやすいように思います。
- 「最初はできなくて当たり前だよ」
- 「ここだけ一緒に見てみようか」
- 「できないところを見つけるのも、大事な勉強だよ」
など、失敗を責めない声かけで心のハードルを下げてあげましょう。
また、チャレンジタッチの場合は、AI国語算数トレーニングで前の学年にさかのぼって復習するのもおすすめです。
時間管理が苦手なタイプ|やりたいけど間に合わない
「やろうと思ってたけど、気づいたら寝る時間…」
こんなふうに、やる気はあるのにスケジュール通りに動けず、進研ゼミが後回しになってしまう子もいます。
特に低〜中学年では、「いつやるか」を自分で考えるのはまだ難しいもの。



気づけば時間がなくなり、「できなかった」という結果が続くことで、やる気も下がってしまいます。
- 朝の支度が終わったら1レッスン
- おやつのあとに10分だけチャレンジ
- 夕飯前の5分間に1問だけ
など、生活の流れに組み込んで「いつやるか」を固定してあげることで、スムーズに取りかかれるようになります。
「時間がないからできなかった」を減らしてあげることで、「やれた!」という自信につながります。
反抗期タイプ|素直に動けない時期かも
「今やろうと思ってたのに!」——
親が声をかけたとたん、反発されてしまう。そんな経験はありませんか?
このタイプの子は、いわゆる“プチ反抗期”の入り口かもしれません。
成長するにつれて、「親に言われたことは素直にやりたくない」という気持ちが芽生える時期です。
我が家の長女も、小学3〜4年生の頃にこの傾向が強く出ていました。



わが家の長女は、「今日やるんじゃなかったの?」「やってないよね?」という言い方をすると、必ずと言っていいほど反発が返ってきます。
- 「今日は国語と算数、どっちからやる?」
- 「チャレンジタッチ、今と夕方ならどっちがいい?」
- 「今日1つだけやるなら、どれにする?」
こうした“自分で決めた感”があると、驚くほど素直に動けることがあります。
反抗しているように見えても、「決めつけられる」のが嫌なだけ。
ちょっとした声かけの工夫で、やる気スイッチが入りやすくなります。
進研ゼミを続けるコツ7選
進研ゼミが続かないのは、子どもなりの理由があるから。
でも、ちょっとした工夫で変わっていくこともたくさんあります。
ここでは、わが家で実際に効果のあった“続けるコツ”を7つ紹介します。
コツ①|ごほうびと達成感を“見える化”する
進研ゼミを続けるコツのひとつが、「がんばりの見える化」です。
子どもは、成果が目に見えると「もっとやろう」という気持ちになりやすいもの。
進研ゼミには、ごほうびシールや努力賞など、モチベーションを支える仕組みがたくさんあるので、活用していきましょう。
わが家で効果のあった“見える化”の工夫
- ごほうびシールのストーリー活用
-
進研ゼミの紙教材には、シールを貼ると物語が進む仕掛けが。
「え、次どうなるの?」「貼ったら教えてね!」と声をかけると、子どもが先を楽しみに自分から動くようになりました。
- オリジナルごほうび制度でモチベUP
-
子どもによっては、ゼミのシールだけでは物足りないことも。
わが家では
- 「1問できたらチョコ1粒」
- 「1ヶ月やりきったら本を1冊」
などの“プチごほうび”を用意してみました。
- 努力賞ポイントで“目標設定”を明確に
-
「あと○ポイントでこれがもらえるね!」と一緒にゴールを確認すると、やる気のエネルギーに。
- 「今週がんばったこと」を紙に書いて貼る
-
- 「今週5回達成!」
- 「毎日続けられたね!」
と“がんばりの見える化”をすると、子ども自身の達成感がアップ!



でも、ごほうびって“甘やかし”にならない…?



「ごほうび」は、“努力を認めてあげる方法”と考えてみましょう。
子どもは「ちゃんと見てくれている」「がんばりをわかってくれる」と感じることで、自然と前向きに取り組むようになりますよ。
進研ゼミのごほうび制度やポイント制度は、活かし方次第で大きな差が出るもの。
まずは、できたことに注目しながら、ひとつずつ“見える形”で認めてあげることから始めてみてくださいね。
コツ②|小さな選択肢を与えて「自分で決める」
子どもは「やらされる」と感じると、どうしてもやる気をなくしてしまいます。
でも、「自分で決めた」と思えると、不思議と動けるようになるんです。
「どっちにする?」が効いた長女のケース
「進研ゼミ、今日やるって言ってたよね?」とストレートに聞くと、「今やろうと思ってたのに!」と怒るのが定番返事。
でも、「今日は国語と算数、どっちからやる?」と聞くと、「えー、じゃあ国語!算数は難しいから後にする」と、意外と素直に動いてくれるんです。
ちょっとしたことだけど、「どれをやるか」を自分で決めることで、やる気スイッチが入りやすくなるのを感じました。
「選ぶ楽しさ」がやる気に変わった長男の場合
まだ学習習慣が定着してない長男にも、「今日はミッション、どれにする?」「どのアプリに挑戦してみる?」と、
選ばせるだけで楽しそうに始めることが増えました。
さらに、できたら「自分で選んでがんばったね!」「自分で決めたってカッコいいね」と声をかけると、自信もアップ!
選ばせるといっても、大きな決断をさせる必要はありません。
- 「どの教科からやる?」
- 「朝と夕方、どっちにやる?」
- 「チャレンジタッチのアプリ、今日はどれにする?」
こうした小さな選択肢を与えるだけでも、自分でやる気持ちを引き出すきっかけになります。



そんな小さな選択で変わるの?



実はこれが意外と効果大なんです!
わが家でも、「どっちにする?」と聞くだけで子どもがスッと動いた場面が何度もあります。
コツ③|子どもに合った“やれる時間”を探す
「毎日やらせたいのに、なかなか進研ゼミに取り組んでくれない…」
それ、やる気の問題ではなく、“時間帯が合っていない”だけかもしれません。
- 朝の支度が終わったあとにサクッと10分
- おやつのあと、ちょっと落ち着いた時間に1レッスン
- 遊び終わって満足した夕方に5分だけ
- テレビや宿題が終わった寝る前にアプリ1つだけ



でも、朝も夕方もバタバタで決めづらいなあ



無理に決める必要はありません!
まずはお子さんが比較的落ち着いている時間帯に、「このタイミング、合うかも?」と観察してみるのがおすすめです。
わが家の長女のベストタイムは「朝」
長女は、学校から帰ってきたらのんびりしたいタイプ。
なので、
『朝の支度が終わったらチャレンジをやる』というルーティンを作りました。
長女自身が、夕方やるよりも朝やった方が自分に合っていることを実感しているので、朝は集中して取り組めています。
「やらなきゃいけない」が「もう済ませた」に変わるだけで、親も子どもも気持ちに余裕が持てました。
長男は「遊びのあと」がゴールデンタイム
長男は朝が苦手。遊びたい気持ちが少し落ち着いた夕方がベストタイミングでした。
夕飯前のちょっとした空き時間に、「チャレンジどうする?今ならできそう?」と声をかけると、意外と素直に取りかかってくれることが多いです。
時には、夕飯を済ませてテレビも見て、1日のやりたいことが全て終わったら、「タッチやるね」と自分からやることもあります。



このように、お子さんが取り組みやすい時間帯を一緒に探してあげましょう。
「やらせる時間」ではなく、「やれる時間」を見つけること。
それだけで、子どもが驚くほど素直に動き出すことがありますよ。
コツ④|点数より「取り組む姿勢」をほめる
進研ゼミを続けるうえで、とても大事なのが「何をほめるか」です。
でも、
- 「やろうとした気持ち」
- 「集中していた時間」
など、“取り組む姿勢”を認めてもらえると、子どものやる気はグッと上がります。
- 「今日、自分から取りかかったのすごいね!」
- 「途中であきらめずに頑張ってたね」
- 「昨日より集中してたよ!」
- 「難しいところにもチャレンジできたね」



でも、うちの子はまだ結果が出てないし、何をほめれば…?



結果が出ていなくても、「行動」に注目してほめることがポイントです。
「やったことを見てくれてる」と感じるだけで、子どもは満足げな表情になりますよ。
「ちゃんと見てくれてる」実感は、子どもにとって最高のごほうびです。
結果よりも“がんばった過程”に目を向けることで、子どもは自信を持って前に進めるようになります。
コツ⑤|親は「教える人」より「応援団」でいる
進研ゼミを続けてもらおうとすると、「ちゃんとやらせなきゃ」「全部見てあげなきゃ」と親のプレッシャーも高くなりがちです。
でも、続けるために本当に大切なのは、“教える”より“応援する”姿勢だと感じています。
- 「そのアプリ楽しそう!ちょっと見せてもらってもいい?」
- 「すごい!そこまで進んだんだ!やったね!」
- 「今日のシール貼ったら見せてね!」
こうした“見てるよアピール”や“喜びの共有”が、子どもにとって大きな励みになります。



でも、ちゃんと教えなくていいの…?



もちろん、教えたくなる気持ちはよくわかります。
でも、子どもが自分で動けるようになるには、見守ってもらえる安心感が必要なんです。
コツ⑥|一緒に楽しむ“実況スタイル”の声かけ
子どもが進研ゼミをなかなかやらないと、つい「やりなさい」と言ってしまいがち。
でも、わが家でいちばん効果があったのは、“一緒に楽しむスタイル”の声かけでした。
たとえば、進研ゼミの教材は、ストーリー仕立ての問題が多く、キャラクターも魅力的。
これを親子で実況中継のように楽しむことで、「やらなきゃ」が「やってみたい」に変わっていきました。
実際には、こんな声かけをしました。
- 「えっ、この話おもしろいね!どうなるのかな?」
- 「え〜そんな展開!?次も気になる!」
- 「そのキャラ、だんだん成長していくんだね!」



でも、親が入っていったら嫌がられそう…



実は逆です。
「ちょっと見せて」「これおもしろそう」と言ってもらえると、子どもは“見てほしい気持ち”が高まっていることも多いんです。
わが家の長女も、
- 「シール貼ったよ!見て見て!」
- 「このキャラこうなるんだよ!」
と、自分から話してくれるようになりました。
親がちょっとワクワクしてみせるだけで、子どもはグンと前向きになります。
コツ⑦|命令をやめて“共感&提案型”に変える
- 「早くやりなさい」
- 「まだやってないの?」
つい言ってしまいがちなこの言葉、実は子どものやる気を下げてしまう“逆効果な声かけ”かもしれません。
たとえば、こんな声かけが効果的です。
- 「今日はどれにチャレンジする?」(=提案)
- 「難しいけど、ここまでやれてるのすごいね」(=共感)
- 「このアプリ面白そう!ママもやってみようかな〜」(=巻き込み)



でも、優しい声かけだけで本当に動くの…?



「やりなさい」と言われると反発したくなるのは、大人も子どもも同じです。
選択肢を与えたり、「がんばってるね」と気持ちに寄り添ったりすることで、“やってみよう”と思える雰囲気が自然と生まれてきます。
命令ではなく、提案と共感を。
それだけで、子どもがぐっと動きやすくなること、本当に多いです。
「家だと勉強しなくて困っている」という方には、こちらの記事もおすすめです。
まとめ|進研ゼミは“続け方”次第!今すぐできる工夫から始めよう
進研ゼミが続かないのは、決して特別なことではありません。子どもなりの理由やタイミングがあるんです。
今回は、進研ゼミを続けるコツを7つ紹介しました。
「どれか1つでも試してみよう」と思えるところから、ぜひ取り入れてみてくださいね。
無料体験&資料請求してみる!
進研ゼミが本当に合っているか不安な方は、まずは資料で教材の雰囲気を見てみるのがおすすめです。
冬限定キャンペーン中
\1月号受講費1,500円割引/
webでの体験はこちらから!
\今なら最大3,000円割引キャンペーン中/